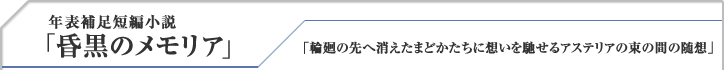
構成・文 菅 正太郎
京乃まどか、フィン・エ・ルド・スイ・ラフィンティ、ムギナミの3人が、ディセルマインの機体と共に、ウォクスもろとも輪廻の向こう側へ消えた……。というより、落ちたというべきかもしれないわね。あるいは取り込まれた…。輪廻を開いたディセルマインの心に―――
モイドは言ったわ―――2万年前のあの日、今ある海がまだ陸地だったここ鴨川で、私が開いた輪廻の先に、"彼の者の声"を待ち望んでいたと。まったくとんだ妄想ね。しかし、あの男は何らかの形で今この瞬間まで命を繋ぎ、再び"声"を聞かんと、文字通り暗雲の立ちこめる2万年前を再来させた。
ええ、分かっているわ。私だって、こんな空をもう一度みるために輪廻の世界から帰って来たワケじゃないもの。私がこの世界に再び来たった理由は、ただひとつ―――2万年前、自分が引き起こした悲劇を繰り返さないためよ。自分の仕出かした過ちを見定め、今を生きる者たちの助けとなろうと決めたの。美味しいものを食べに戻って来たワケではないわ。
でも、正直なところ、まさか自分以外に2万年の時を経た人間がいるとは、思ってもみなかった。ユリカノが、「ミリティア・ゾデアの惨劇」を引き起こし、輪廻の世界に来るまでの間、私は、絶えることのない波音の中にあった。「あった」という表現がこの場合は相応しいと思う。2万年の間ずっと輪廻の向こうにいた自分が、実体として存在していたのかすら判然としない。時間という感覚を伴うことなく生きていたというべきかしら。今でも、あそこにいた時が、長いとも、短いとも思い出せない。まるで、あそこに流れる時間は、寄せては返す波のように、絶えることなく、永遠に続く円環の中にあるようだった。今思えば、奇しくも輪廻を開くきっかけを作った、最初のウォクスを「イプシエンス」と名付けたことが皮肉に思えるわ。「イプシエンス」それは古い言葉で、全てが始まる場所であり、全てが帰る場所という意味。輪廻を開く前にこんな名前を付けたなんて、なんの因果かしらね。
モイドのことは今更悔やんでも仕方がないことよ。今は、あの男がいつどんな形で2万年の時を越えて来たかを検証すべき時ではない。もちろん、尋問は続けるわ。この事態を回避できる情報をあの男の口から聞き出せるかもしれないし。
× × ×
黒い稲妻がアンテナ塔の先端を破壊して、ブリッジの前を結晶化しながら落ちて行った。2万年前もこんな空だったのかしら。はっきりとは覚えていないの。信頼すべき人々に裏切られ、自分が最も望まぬ形で、ウォクスの力を解放してしまった。それから先は、都合のいい話だけれど、断片化した記憶しかない。
ディセルマインはどうだったのかしら。きっと私と同じはず。濁流にのみ込まれている最中に、自分は濁流にのみ込まれているのだということを認識できたとしても、状況まで把握することはできないわ。私自身もそうだった。崩壊する心は濁流に似ている。右へ左へと勢いのままに翻弄され、それは力が解放されるまで続く。気づいた時には、私の中の感情の高ぶりは消えうせ、私は輪廻の世界で波の音をきいていた。途中のことはよく覚えていないの。でも濁流に飲み込まれる以前のことは忘れていないわ。
× × ×
ノウムンドゥスを「新しい世界」として、旧世界を「ウェトムンドゥス」と呼ぶなら、ウェトムンドゥスでは、今よりもはるかに、今でいう素粒子物理学が発達していて、それらは、総称として「亜空粒子」と呼ばれていた。その研究の果てに、新たな地平を開く万能粒子として「ウォクス粒子」は注目を集めたの。各国がこぞって研究開発する中、最初にウォクス粒子を発見した、私の国「古レ・ガリテ王国」は、初のウォクス搭載型オービッドを建造したという意味では、他を圧倒していたわ。でもそれが他国にとって脅威と映った。まだ何が出来るという訳ではなかったのに、究極の兵器が完成すると、他国は警戒し、緊張はじわじわと高まりつつあった。だから私は決めたのよ。ウォクスの開発を国際的に開かれたものにしようとね。そのために私は、当時ウォクス開発に興味を示していた各国の王たちに書状を出し、国際会議の場で、このことを提案するつもりだった。もちろん彼らにはそれを事前に報告し、あとは「調印」というところまでこぎつけていたの。でもそれが、当時、私が信頼を寄せていた側近たちの琴線に触れた。彼らはウォクスの力を、輪廻のもたらすエネルギーを手中に収め、分かりやすく言えばこの世界を牛耳りたかった。ウォクスという圧倒的「力」を独占出来ればそれも可能だと本気で信じていたのよ。モイドのようにウォクスの力に神様をみるのとはまた違った形で、彼らは彼らで何かに取りつかれていたのよ。
でも当時の私はそんなこと夢にも思わなかった。私は完成したばかりのウォクス・イプシエンスに乗って、エクエスの原型ともいえる6人の従者を引き連れ国際会議の場に赴いた。だがその日に、私の側近たちは私を裏切った。国際会議の場を、私の命令と称して無差別に攻撃を始めたの。当然、各国は混乱の極みの中、私に裏切られたことに反抗した。ただ他国も全面的に私を信用していた訳ではなかった。オプションのひとつとして、こういったことも想定の内に入れていたようね。彼らはあらゆる可能性のひとつとして想定していた最悪のカードがレ・ガリテにより引かれたと、我らに宣戦を布告。レ・ガリテに総攻撃をかけたの。私は遠く離れた国際会議の場で、イプシエンスのコクピットを通じて、祖国に生きる民たちの阿鼻叫喚を聞いた。私の心は怒りに震えた。だが一方で目の前では、私の国の者が他国の人間に対して同じことをしている。私は戦争状態を回避しようと、奔走したわ。でも私自身が攻撃の対象でもあったがために、私は仕方なく応戦した。とても多くの人の命を奪ったはずよ。そうする中で、いつしか私の心はかき乱され、結果としてウォクスの力を自分の望まぬ形で解放させてしまったの。
あの事象にモイドがどう関わっていたのかは分からない。その昔、まだウォクスをオービッドに搭載する以前、ウォクスコアとして研究開発を行っていた頃、私たちはよくウォクス粒子が搭乗者の心に及ぼす影響を議論し合った。その時に、こんなことを進言した学者がいたの。「人の心は粒子と同じように目に見えるものではない。ということは、心もまた粒子でできているのではないか」とね。あの者の名前はなんといったかしら? ダメね。顔すら思い出せない。あるいはあれがモイドだったのかもしれないわね。
× × ×
つまるところ、ウォクスとは、心を映す鏡のような働きをすることだけは否定しようがない。搭乗者の心に強く作用し、言いかえれば、作用できる心にしかメモリアしない―――それがウォクス粒子。
今、あの輪廻の中で、五つのメモリアがひしめき合っている。まどか、ラン、ムギナミ、それとディセルマイン、残るひとつはユリカノ。この五人の心のありようが、輪廻の世界を、ひいてはこの地球を、この宇宙の在り方を決めることになる。
ランは兄をもう一度王として尊敬することが出来るかしら。ムギナミは、ヴィラジュリオに手をかけたディセルを許すことが出来るかしら。まどかはあの子の生き方として、ジャージ部として、ディセルを受け入れることができるかしら。
ウォクスを支配する。それは己の心を律することに近しいといえる。表層意識にとどまらず、深層意識に至るまでコントロールできなければ、ウォクスの暴走と言う可能性は永遠に消えることがない―――
違うわね。
あの子たちにとって、ウォクスは支配するものなんかじゃない。とても信頼を寄せる友達のよう。おそらくそれが、私とも、ディセルとも、ユリカノとも違うところ。
私はあの子たちのように、ウォクスと話をしたことがないのかもしれない。ウォクスはウォクスなのであり、それ以上でもそれ以下でもない。私のように恐れることも、モイドのように敬うこともない。私はウォクスのことを、実は何も知らないのかもしれない。
もしもあの時、誰よりも優しいアナタが生きていれば、私はきっとそのことに気付けていたのでしょうね。
× × ×
いまだ空は、太陽の光の入りこむ隙間もないくらいに暗い雲が立ち込めている。「怖くないの?」私は隣に立つようこに尋ねた。そうしたら彼女は「怖くないと言えば嘘になる」「でもね―――」といつもの言葉を口にした。私はまどかを信じると。
2万年前のあの日、何故、モイドの望むような形で宇宙はその理を変えなかったのか、実は誰も答えを持っていない。輪廻の向こう側に取り込まれた私にも記憶は断片的にしか残ってはいない。でもひとつだけ確かなことがあるとすれば、感情の濁流から、輪廻の海に放出された時、すでに私の心には不安も怒りも悲しみも自分を支配していた恐ろしい気持ちが全て消えうせていた。私は感情をどこへ置き忘れてきたのよ。
それはどこなのかしら。
アウラ、リンファ、イグニス―――風と水と炎と名付けられた三体の機体は、あの時、私を支配していた私の三つの心だったのかもしれない。王女としての私、女としての私、そして、こうありたいと願い続けてきた私―――複雑に絡み合った三つの心が、私をかき乱し、輪廻を開かせた。その絡み合った心を、私自身の僅かな理性が分裂させたのか、それともイプシエンスがそれを促したのかは、今となっては分からない。
待つとしよう。あの子たちを。
私の知らない、本当のウォクスを―――
―――終わり










